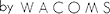お肌の潤いを保つためには、肌の水分量を高めることが大切です。
水分量の少ない肌は、乾燥による肌トラブルを引き起こします。
この記事では、肌の水分量を高め、ハリや弾力を保つための生活習慣やスキンケアのポイント、保湿に役立つ成分を、さまざまな論文やエビデンスを元に詳しく解説します。
また、男性肌は女性に比べて皮脂が多く、皮膚バリア機能が低い肌荒れ傾向であることがわかっています。1
女性はもちろんのこと、肌の水分量をあげたいメンズにもおすすめの記事内容です。
お肌の水分量を上げる生活習慣のポイント

日々の習慣を見直すことで、肌の水分保持力をサポートし、乾燥しにくい肌環境を作ることができます。
肌の水分量は何パーセントが理想だと思いますか?
答えは、20~30%ほどといわれています。
これを維持することで、肌のハリと弾力が保ちやすくなります。
生活習慣を整えることで、ターンオーバーを正常に促し、乾燥やくすみを防ぎ、肌の水分量を保つ効果が期待できます。
具体的に生活の中で気をつけるポイントをご紹介します。
水分補給
一般男性の身体の約53%、一般女性の身体の約45%が水分で構成されています。
1日に飲む水の量が、肌のうるおいや健康と関係があるという考え方は、日常生活だけでなく医療の現場でも注目されています。
1日に必要な水分摂取量とは?
液体としての水分補給に必要な量は20代男性で1日約1.8L、20歳代女性の場合では1日約1.4Lです。
運動量、年齢、体格などの個人差や、季節、気温・湿度などの環境によっても必要な水分量は変わるので、あくまで目安です。
20代男性では、1日の水分摂取の目安は3.6Lとされます。
しかし、体内のエネルギー代謝により約0.4Lの水が作られ、呼気などからも水分が入ります。さらに、大体の食品には水分が含まれているため、しっかり食事をするだけでかなりの水分をとることができます。
日本人の場合、一般的な食事を3食とると3.6Lの水分のうち約半分を摂取していることになるのです。2
水分補給と肌の潤いに関する研究結果
肌の潤いに水分補給はどのように関係しているのでしょうか。
2015年の研究では、健康な女性49名を対象に、日常の水分摂取が肌の状態にどのような影響を与えるかを調べました。
この研究から、普段あまり水を飲まない人は、食事を通じて多めの水分を摂ることで、肌の状態が改善される可能性があることが分かりました。
特に、肌の乾燥に悩む高齢者や肥満の方において、薬を使わずに水分摂取だけで肌の潤いを改善できれば、生活の質が大きく向上すると考えられます。
普段より多く水分を摂ることで皮膚が潤い、柔軟性やなめらかさが改善する可能性が示唆されました。
特に、肌が乾燥しやすい人には効果が期待できると結論づけています。3
しかし、実際に水を多く摂ることが本当に肌の改善につながるかについては、まだエビデンスが少ないのが現状です。
2018年の文献レビューでは、過去に行われた研究を調査しました。
全体として研究数は少なかったものの、それらの研究をみると、水分摂取量が少なかった人が水を多く飲むことで、肌の表面(角質層)と肌の奥(深層)の水分量がやや増えることがわかりました。また、乾燥や肌荒れの症状が軽くなったり、肌が柔軟で伸びやすくなったりする効果も少し見られました。
一方、水を多く飲んだことによる皮脂量や肌表面のpHなどへの明確な影響は確認できませんでした。
食事から摂る水分を増やすことは、肌の水分量を増やす可能性がありますが、なぜ増えるのかという詳しいメカニズムはまだわかっていません。また、高齢者にも同じ効果があるかどうかや、水分摂取が実際に乾燥肌を改善するのかについては、今後さらに研究を進める必要があると結論づけています。4
バランスの良い食事
肌を良い状態に保つには、身体の内側からアプローチしましょう。
皮膚を強くするビタミンA、ビタミンB、ビタミンCなどの栄養素は、ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜に豊富に含まれます。
活性酸素の除去作用があるビタミンE、リコピン、カロテノイドなどは、以下の食材に含まれます。
| ビタミンEを多く含む食材 | ひまわり油、べにばな油、アーモンド、ヘーゼルナッツ、落花生、ピーナッツバター、たらこうなぎ白焼き、かぼちゃ、大根の葉 赤ピーマン、とうがらし、マヨネーズ(全卵型)、抹茶 |
| リコピンを多く含む食材 | ミニトマト、トマト、スイカ、ピンクグレープフルーツ、ピンクグァバ、柿、金時人参 |
| カロテノイドを多く含む食材 | ジャガイモ、にんじん、緑の葉野菜、かぼちゃ、赤唐辛子、アプリコット、トマト、マンゴー、オレンジ、スイカ |
また腸内環境を整えることも肌の調子を整えるのに有効です。ヨーグルトや味噌、納豆、酢などの発酵食品を積極的に摂りましょう。
悪玉菌により腸内環境が悪くなると、肌の弾力やハリ低下、くすみ、肌荒れ、吹き出物などにつながります。5
これらのあらゆる栄養素をバランスよく摂ることが大切です。
カロテノイド(リコピン)について今記事の段落で詳しく解説しています。 >>
UV対策
紫外線はじわじわと私たちの肌に影響を与えます。
紫外線を防ぐには「紫外線を浴びないこと」が一番です。日焼け止めを塗るほか、ツバの広い帽子をかぶる、日傘をさす、アームカバーをつける、サングラスをかけるなど、紫外線を浴びない工夫をしましょう。
そもそも紫外線ってなに?
地上に届き人に影響を与える紫外線にはB波とA波があり、それぞれ特徴が異なります。
紫外線B波(UVB)は、日光浴で肌が真っ赤になるなどの日焼け(サンバーン)の主な原因です。
UVBはエネルギーが強く、皮膚の細胞を傷つけ炎症を起こし、皮膚がんやシミの原因にもなります。
しかし、地上に降り注ぐのは全紫外線の10%程度です。
紫外線A波(UVA)は、すぐに肌が黒くなる日焼け(サンタン)を引き起こします。
皮膚の表皮より深い真皮まで影響を与えます。
真皮では、エラスチン繊維やコラーゲン繊維が皮膚のキメやハリを維持していますが、UVAのダメージを受けると、シワやたるみなど光による皮膚の老化につながります。67
日焼け止めの効果と塗り方
日焼け止めの効果は SPF(Sun Protection Factor)と PA(Protection grade of UV-A)で記載されています。
SPFは、紫外線B波(UVB)をブロックするためのもので、50+までの数字でUVBを防ぐ効果の目安を表します。SPFは1値ごとに15分〜20分ほどのブロック効果があると言われます。
一方PAは、紫外線A波(UVA)を防ぎます。+マークの数で効果を表しており、4つ(++++)が一番効果が高いです。
日焼け止めの塗り方のコツは、1cm2(平方センチメートル)あたり2mg(ミリグラム)という規定の量をムラなく塗ることです。
SPF値とPA値は、皮膚1cm2あたり2.0 mgの日焼け止め(サンスクリーン剤)を塗布して測定されているからです。
しかし、実際は一度にこの量を塗布できないことも多いため、表示されている効果を得るには重ね塗りが必要です。
また、2〜3時間を目安に塗り直すことも有効とされています。89
メイクをしているとなかなか塗り直すことが難しい時もあるので、UV効果のあるパウダーやスプレーなどを併用してみてくださいね。
スキンケア:洗顔・クレンジング
肌の水分量を上げるためには、適切な洗顔とクレンジングが重要です。
洗顔やクレンジングの目的は、肌の表面に付着したほこりや汚れ、余分な皮脂やメイクを落とし、肌を清潔に保つことにあります。
ただし、強力な洗浄成分を使用すると、肌の潤いに欠かせない皮脂や細胞間脂質まで奪われてしまい、乾燥やつっぱり感を引き起こすことがあるため注意が必要です。
洗顔料は主に次のような種類があります。
| 固形石けん(弱アルカリ性) | 洗浄力が高く、皮脂を取り除く効果が強い一方、肌の乾燥を招く場合があります。 |
| 弱アルカリ性クリームタイプの洗顔料 | 適度な洗浄力と保湿性を両立した製品もありますが、ラウリン酸やオレイン酸を含むものは肌荒れのリスクがあります。ステアリン酸やパルミチン酸を配合したものの方が安全性は高いとされます。 |
|
弱酸性クリームタイプ(アミノ酸系洗顔料) |
肌への刺激が少なく安全性が高いため、敏感肌の方にもおすすめですが、洗浄力が比較的弱いため汚れを落としきれないこともあります。 |
近年の研究では、洗顔によってセラミドなどの保湿成分が流出し、肌のバリア機能や水分保持力を低下させる原因となることがわかっています。
特に敏感肌の方にとっては、弱酸性で皮膚への刺激が少なく、セラミドの流出を防ぐ処方が施された洗顔料を選ぶことが重要とされています。アルカリ性の洗浄剤は、角層タンパクの変性や細胞間脂質の流出を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
正しい洗顔料の使用方法
まず顔をぬるま湯で濡らしてから適量の洗顔料をよく泡立て、肌に優しくなじませて洗います。
その後、ぬるま湯で丁寧にすすぎ、柔らかいペーパータオルなどで軽く押さえるように水分を取りましょう。
水温が高すぎると肌の乾燥を促進し、低すぎると洗顔料が残りやすくなるため、適温(約30~35度程度)で洗うことがポイントです。
クレンジング剤の使用方法
メイクを落とすクレンジング剤は、使用後に必ず洗顔料で再洗顔することが推奨されます。
これは、クレンジング剤や汚れが肌に残ると、肌トラブルの原因になったり、その後のスキンケアの効果を妨げたりするためです。
クレンジング料はメイクとしっかりなじませ、汚れを浮き上がらせたあと、ぬるま湯できれいにすすぎ落としましょう。10
正しい洗顔とクレンジングを習慣にすることで、肌の潤いを守りながら清潔な肌環境を整えることができます。
スキンケア:保湿
肌の水分量を維持するためには、適切な保湿ケアが欠かせません。
保湿ケアは、洗顔後に肌のモイスチャーバランスを整える化粧水から始まります。化粧水には水分だけでなく、保湿剤が豊富に含まれており、肌に潤いを与えます。
化粧水はコットンで使う方法と手で直接塗る方法とで、それぞれ特徴があります。
コットンを使用すると、塗り残しが少なく、古い角層を優しく除去できますが、化粧水がコットンに残ってしまいます。
一方、手で塗布すると、心理的なリラックス効果が期待でき、化粧水を無駄なく肌に届けることができますが、塗りムラに注意が必要です。
どちらの方法でも塗布30分後の保湿効果に大きな差はないため、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。
化粧水は大量に使うよりも、適量を数回に分けて丁寧に塗るほうが効果的です。
また、化粧水の後には乳液やクリームなど油分を含むアイテムでしっかりと保湿し、水分の蒸発を防ぎましょう。
特にクリームは、皮膚表面を覆って水分蒸散を抑えるオクルージョン効果があり、保湿力を高めます。
クリームの使用により肌のバリア機能が改善されることも報告されています。
自分の肌タイプや悩みに合わせて、美容液や乳液、オイルタイプの保湿アイテムを取り入れ、肌の水分をしっかり閉じ込めましょう。(8
オクルージョン効果とは?
オクルージョン効果とは、ワセリンなどの水を通しにくい油分を肌に塗ることで、皮膚の表面に“フタ”をし、体内から蒸発する水分を逃がさないようにする仕組みのことです。
これにより、肌の水分量が保たれ、乾燥を防ぐことができます。11
適度な運動適度な運動
肌の水分量を改善し、美肌を保つためには、適度な運動を生活に取り入れることが効果的です。
2019年の研究によると、肌の水分量と油分量のバランスが崩れることがシミやシワ、ニキビなどの肌トラブルにつながる可能性が示されています。適度な運動は、血行を促進し、肌の新陳代謝を高めるため、水分量と油分量の理想的なバランスを維持するのに役立ちます。
同研究で一般市民マラソン大会に参加した20~60歳代の男女248名を対象に調査した結果、週に1~2回程度運動を行う人が最も理想的な水分量と油分量のバランスを示しました。また、適度な運動は基礎代謝の向上や、自律神経の安定、深い睡眠の促進、成長ホルモンの分泌増加などの効果ももたらします。12
また2015年の研究では、3ヶ月の有酸素運動で65歳以上の高齢者の肌のコラーゲン量とミトコンドリアDNA量が増加し、お肌の老化予防の効果があることがわかりました。13
このため、週1~2回の有酸素運動を習慣化することが推奨されます。運動不足や過度の運動は逆効果になることもあるため、自分のペースで無理なく続けられる運動を取り入れ、健康で潤いのある肌作りを目指しましょう。
禁煙
健やかな肌を保つためには、禁煙も重要な習慣のひとつです。
喫煙は血行を悪化させ、肌の水分量を低下させるだけでなく、皮脂分泌を増やし、ニキビや毛穴の開き、かさつきやかゆみといったさまざまな肌トラブルを引き起こすことがわかっています。
大規模な調査研究では、20〜50歳の女性約19万人を対象に喫煙と肌状態の関係を分析した結果、喫煙は非喫煙者に比べて角層の剥離量やメラニン量が多く、肌のバリア機能が低下していることが示されました。
また、喫煙者は肌が脂っぽく、乾燥しやすく、ニキビやかゆみを感じやすい傾向にあることも明らかになっています。14
別の研究では、喫煙習慣のある人は水分量が低く、油分量が高くなる傾向が示されており、肌の潤いと皮脂バランスに悪影響を及ぼすことが統計的にも確認されています。(12
さらに、25歳以降は喫煙による肌へのダメージが加速し、特にメラニン量の増加が著しく、シミの原因となることが報告されています。喫煙によって角層細胞のターンオーバーが乱れることで、肌のかさつきや敏感肌のリスクも高まります。
こうしたことから、禁煙は肌の水分保持力やバリア機能を守るうえで非常に重要であり、美容面からもその効果は大きいと言えるでしょう。
質のいい睡眠をとる
美しい肌を保つためには、質の良い睡眠をしっかりと確保することが大切です。
肌の水分量は、日々の睡眠の質や量と密接に関係しており、特に6〜8時間の睡眠が最も理想的であることが複数の研究から示されています。
2019年の調査では、睡眠時間が6〜8時間の人は水分量が最も高く、それ以上睡眠をとっている人では水分量の減少が見られました。また、皮脂量についても9時間以上の睡眠で減少する傾向が報告されています。(12
さらに、株式会社ポーラの「美肌県グランプリ2020」では、水分量が多い上位3県(石川県、広島県、和歌山県)に共通していたライフスタイル要因として「朝すっきり起きられる=質の良い睡眠」が挙げられました。
これは、自律神経が整って副交感神経が優位になることで、就寝中に肌へ栄養や酸素がスムーズに届けられる状態が維持されていることを意味しています。15
また、2023年の実験では、睡眠不良の被験者は目元や頬の水分量が明らかに低下しており、肌の柔軟性の低下や角層タンパク質の状態変化も確認されています。これにより、乾燥やごわつき、化粧ノリの悪さといった肌トラブルを引き起こす可能性が示唆されました。
特に入眠時間が遅くなることは、睡眠の質の低下に直結し、肌の代謝にも悪影響を及ぼします。入眠前にはスマホやタブレットの使用を控え、ぬるめのお湯で入浴したり、照明を落として副交感神経を優位にするなど、リラックスできる環境づくりが重要です。16
肌の保湿と並行して、日常の中で「よく眠るための工夫」を意識することが、内側からうるおいを引き出すスキンケアの一部といえるでしょう。
加湿する
肌の水分量を保つためには、室内の湿度管理が重要です。
特に冬場は暖房の使用により空気が乾燥しやすく、湿度が50%を下回ると肌が乾燥しやすくなると言われています。
逆に湿度が60%を超えると肌の乾燥感が大きく緩和され、肌の状態が良好に保たれる傾向があります。
2013年の実験では、湿度30〜40%と比較して、60〜70%の環境では非敏感肌・敏感肌問わず肌の乾燥感が明らかに軽減し、水分量も高く保たれることが確認されました。湿度が高い環境では、水分の蒸散量が減少し、角層のうるおいが維持されやすくなるためです。17
2014年の実際の被験者実験では、エアコン使用時の暖房環境下で湿度を65%に保った条件では、肌の水分量が有意に高く保たれたという結果も報告されています。逆に加湿をしなかった条件では、皮膚の水分量が急激に減少し、乾燥感を感じやすくなる傾向がありました。18
ただし、湿度が70%を超えるとカビの発生など健康への影響も懸念されるため、過度な加湿は避け、60〜65%前後の湿度を目安にこまめな換気を取り入れながら快適な環境を維持するよう心がけましょう。
加湿の方法としては、加湿器の利用が最も効果的ですが、濡れタオルや水を入れたコップ、室内干しや観葉植物などでも一定の効果が得られます。浴室の扉を開けておく、鍋料理を楽しむといった生活の中で取り入れやすい工夫もおすすめです。
肌の水分量を上げる成分

保湿に役立つ成分を取り入れることで、肌の水分保持能力を根本からサポートすることができます。
これらを上手に活用することで、肌が自ら持つバリア機能や修復力を高め、水分量を安定させることが可能です。
セラミド
セラミドは角質細胞の間を埋める細胞間脂質の一種で、外部刺激から肌を守りつつ水分を保持する重要な機能を担います。
セラミドは加齢やストレスで減少しやすいため、スキンケア製品で積極的に補うことが大切です。セラミドがしっかり補充されると、乾燥や刺激から肌を保護するバリアが強化され、しっとりとした感触が持続します。
実際に、敏感肌の人は非敏感肌に比べてセラミド量が少なく、皮膚の水分蒸散量(TEWL)や角層水分量にも悪影響が見られることが報告されています。また、アトピー性皮膚炎やニキビ(尋常性ざ瘡)を持つ人も、角層中のセラミド量が減少し、その質の変化(例えば炭素鎖の短鎖化など)によってバリア機能が低下する傾向があります。
こうした背景から、セラミドを含むスキンケアは敏感肌や乾燥肌対策として非常に有効とされています。特に、角層バリア機能が低下した状態では、外用によってセラミドを補給することで、角層水分量が回復し、バリア機能も改善されることが実証されています。
さらに近年では、天然セラミドと構造が類似する“擬似セラミド”が開発され、化粧水やクリームなどに応用されています。この擬似セラミドは、角層内の天然セラミドと同様にラメラ構造を形成して水分を保持し、乾燥性敏感肌や脂性敏感肌、アトピー性皮膚炎に対する有効性も示されています。
擬似セラミド配合クリームの使用により、角層水分量やセラミド量の回復、水分蒸散量の改善、さらに肌刺激に対する感受性の低下も確認されています。肌にうるおいとバリア機能を取り戻すためには、こうしたセラミドを取り入れたスキンケアの継続が効果的です。(10
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸は体内のさまざまな組織に存在し、その約50%が皮膚に分布しています。
水分をたっぷり抱え込む性質を持つため、肌のうるおいやハリを保つうえで欠かせない成分ですが、加齢や紫外線によって減少し、乾燥や小じわを引き起こす要因となります。
2019年の研究では、分子量30万または80万のヒアルロン酸を6週間摂取した結果、乾燥肌を自覚していた健康な女性において角層水分量の増加が確認され、特に分子量30万のヒアルロン酸では摂取終了2週間後にも水分量が有意に増加していたことが示されました。19
また、紫外線照射を受けたマウスに対する実験では、ヒアルロン酸摂取により皮膚水分量の低下が抑制され、光老化の予防効果も認められました。さらに、美容医療の分野では、ヒアルロン酸を直接肌に注入することでシワの改善にも利用されており、注入後すぐにハリやふくらみを実感できる即効性が特徴とされています。20
これらの知見から、ヒアルロン酸は経口摂取によっても外用によっても、肌の水分保持力をサポートし、乾燥やエイジングサインの対策に役立つ成分であることがわかります。
アロエベラ(アロエステロール)
アロエベラは、古くから火傷や傷の手当に用いられてきた植物ですが、近年の研究により、アロエベラ由来の成分「アロエステロール®」が、肌の水分保持や弾力性の向上に役立つことが明らかになっています。
2016年の森永乳業と和歌山県立医科大学との共同研究では、アロエステロール®を含むヨーグルトを摂取した被験者において、皮膚の水分蒸散量(TEWL)が有意に減少し、皮膚の粘弾性や全体の弾力性が有意に増加したことが確認されました。つまり、アロエステロールは肌のバリア機能を強化し、水分が蒸発しにくい潤った肌を維持する働きがあると考えられます。
さらに2019年、真皮層のコラーゲン量に着目した検証では、アロエステロール摂取群において、摂取前より有意にコラーゲンスコアが上昇し、対照群との比較でも有意差が認められました。これにより、アロエステロールがコラーゲンの生成促進と分解抑制の両面から真皮の構造維持に寄与している可能性が示唆されました。
こうした研究成果は、アロエステロールの経口摂取が肌のうるおい、弾力、バリア機能の維持に効果的であることを示す科学的根拠となっています。2122
アロエステロールを含む食品やサプリメントを上手に取り入れることで、内側から肌を整えるサポートとして活用できるでしょう。
コラーゲンペプチド
コラーゲンペプチドは、皮膚の保湿や弾力性の向上に役立つ成分として注目されています。
コラーゲンはもともと皮膚や骨、軟骨など体内に多く存在するたんぱく質であり、その構造の特徴から細胞の足場としても働き、皮膚の弾力やハリを支える重要な役割を担っています。
このコラーゲンを加水分解して低分子化したものがコラーゲンペプチドであり、体内に吸収されやすくなることで、機能性食品としても広く活用されています。
2009年に行われた臨床試験では、魚由来の鱗コラーゲンペプチドを4週間摂取した結果、30歳以上の被験者では、5g以上の摂取で角層水分量の有意な増加が認められました。一方、豚皮由来のコラーゲンペプチドでは明確な効果は見られず、原料の違いによって肌への影響にも差が出ることが示唆されています。23
さらに2010年のヒト試験では、乾燥肌に悩む女性を対象に、1日2.5g、5g、10gのコラーゲンペプチドを4週間摂取させたところ、用量に比例して角層水分量の増加が見られました。5g摂取群では41%、10g摂取群では62%の被験者が肌状態の改善を実感したと報告されており、体感性の高さも注目されています。
また動物実験では、紫外線を浴びたマウスにコラーゲンペプチドを摂取させた結果、肌の水分量低下やコラーゲン減少が抑えられたことが確認されており、コラーゲンペプチドが外的ストレスから肌を守る働きも期待されています。24
このように、コラーゲンペプチドの継続的な摂取は、肌のうるおいや弾力の維持に有効であり、特に年齢による肌機能の低下が気になる方にとって、内側からの美容ケアとして有望な選択肢のひとつです。
カロテノイド(リコピン)
リコピンは強力な抗酸化作用を持つカロテノイドの一種で、トマトやスイカ、柿などに多く含まれる赤い色素成分です。
ビタミンEの約100倍、β-カロテンの2倍とも言われるその抗酸化力により、体内で発生する活性酸素を除去し、動脈硬化や各種がん(前立腺がん、胃がん、肺がん、子宮がんなど)の予防にも寄与すると考えられています。2526
肌に対するリコピンの効果も多数報告されています。カゴメと複数の研究機関による研究では、リコピンを摂取したマウスにおいて、角層の水分量低下と皮膚の炎症が抑制されたことが確認されました。27
また、人を対象とした研究では、放射線治療後の乳がん患者にトマトジュース(リコピン16mg含有)を6か月間飲用させたところ、皮膚の乾燥が抑制され、水分量が回復する傾向が見られたと報告されています。28
さらに、リコピン配合サプリメントを3か月間摂取した研究では、肌のバリア機能(経表皮水分蒸散量: TEWL)が統計的に有意に改善し、シワ、肌の色調、ハリ、毛穴の目立ちにも有意な改善が見られました。29
このことから、リコピンは内側からの肌ケアにも非常に有効であることが示されています。
加えて、リコピンを局所に塗布する形(リコピンエマルゲル)でも、皮膚の水分量と弾力性が有意に向上し、紅斑やメラニン量も減少したという報告もあります。 30
これらの結果から、リコピンは経口摂取でも外用でも、肌の水分量の保持、バリア機能の強化、シワやくすみなどの予防に役立つ可能性が高い成分と考えられています。
大豆イソフラボン
大豆イソフラボンは、大豆の胚芽部分に多く含まれる植物性ポリフェノールで、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きを持つことから「フィトエストロゲン(植物エストロゲン)」とも呼ばれています。
体内での作用はエストロゲンの約1/1000〜1/10000と穏やかですが、加齢や無理なダイエットなどによるエストロゲン減少を補い、肌の健康維持に寄与します。(25
エストロゲンは、皮膚のコラーゲンやヒアルロン酸産生を促進し、水分保持や弾力性の維持に重要な役割を果たしています。そのため、大豆イソフラボンの摂取によって、肌のうるおいやハリを保つ効果が期待されています。
ダイセル社との共同研究によるヒト試験では、大豆イソフラボンとラクトビオン酸を同時に摂取した女性たちで、乾燥する季節にも角層水分量の維持・改善、経皮水分蒸散量(TEWL)の低下、肌の弾力性の維持・向上が確認されました。この成果は特許も取得されています。31
さらに、大豆イソフラボンには、エストロゲン過剰時にはその作用を抑える抗エストロゲン効果もあり、更年期症状の軽減や、がんリスク低減にも寄与するとされています。
摂取目安は、1日あたり約40mgが推奨されています。骨粗しょう症の予防や肌の健康維持のためにも、若いうちから積極的に大豆製品(豆腐、納豆、豆乳など)を取り入れましょう。
お肌の水分量について最近の研究でわかってきたこと

皮膚をやさしく調べる光の技術を使ってお肌のうるおいを調べた「分光測定に基づくヒト表皮水分の評価」という2017年の論文をご紹介します。
この研究は、皮膚のうるおいが「どこに(深さ)」「どこで(部位)」変わるのか」を、特別な光でしらべたものです。32
お肌の水分量について調べた方法
お肌の水分量について調べた方法は2つあります。
1.皮膚の中の深さをちょっとずつ調べた
「自発ラマン散乱分光法」という光を当てる方法で、皮膚の2ミリずつくらいを深く見ながら、それぞれ何%潤っているかを測りました。
2.顔の水分量を場所ごとに調べた
近赤外線カメラを使って、顔全体の表皮水分量の評価を行いました。
例えば、水分が多い場所は「青」、乾燥してる場所は「赤」などに色分けし、 どの部分が乾燥しやすいかマップにして一目でわかるようにしました。
お肌の水分量についてわかったこと
お肌の水分量についてわかったことは4つあります。
1.うるおいは、皮膚のすごく浅いところで変わっているだけ
皮膚の水分量は部位や季節、年齢によって異なることが確認されました。
しかし冬の低湿度など外部の環境で変化するのは、表層わずか数μm(マイクロメートル)でした。
深部の角層(中下層)は、季節や環境ではほとんど水分量が変わらないままでした。
人が感じる肌感覚に重要なのは、薄い角層のさらに上層部分の変化であることが示唆されました。
2.顔でも乾きやすい部分がある
目のまわり、頬の下あたりは、他の部分よりもかなり水分が減りやすいことがわかりました。
対して、耳の近くなど顔の端のほうは乾きにくい可能性があります。
3.顔面水分量が一番少なくなる季節がある
東京近郊に住む26名の健常女性を対象に、冬・春・夏・秋それぞれの顔の水分量を計りました。
その結果、一番水分量が減りやすい季節は、冬ではなく秋であることがわかりました。
秋には目のまわりの水分量がかなり少なくなることも確認しました。
4.水分のなじみ方には、人それぞれの個性がある
高帯域近赤外カメラと専用の光源を使用した結果、皮膚へ水をつけた時に、すぐ水を吸い込む人となかなか吸わない人がいることも分かりました。
今後、個人の肌質の「水分の馴染みやすさ」がわかるようになるかもしれません。
この研究からわかること
この研究で画期的なところは、皮膚を傷つけずに、どこがどれくらいうるおっているか、「深さ方向」と「面方向」の両方から分かることです。
化粧品や薬の効果を正確にチェックでき、肌が乾燥してるという感覚を、数字や画像で視覚化できる可能性があります。
従来の「角層=水分が一様」という常識を覆し、より科学的な肌評価の道を開きました。
光を使って、「どの深さ」の水が変わるのか、「顔のどこ」が乾きやすいのか、「肉眼ではわからない肌質」があることを、クリアに分析できるようになりました。
これは、今後のコスメの研究や皮膚治療薬の効果検証にも役立ちそうです。
お肌の水分量を上げるためには生活習慣とスキンケアの対策を!

肌の水分量を高めるためには、生活習慣とスキンケアの両面からのアプローチが重要です。
体内からの水分補給と、栄養バランスのとれた食生活を基本としながら、紫外線対策や適切なスキンケアを組み合わせることが、うるおいを守るカギとなります。
また、セラミドやコラーゲン、リコピン、大豆イソフラボンなど、肌のバリア機能や保湿力を高める成分を積極的に取り入れることも効果的です。
とくに水分補給は、肌の健康維持に欠かせません。乾燥を感じてからでは遅いため、こまめに水を飲む習慣をつけましょう。目安としては1日あたり1.4〜1.8リットルを目標に、少量ずつでもこまめな補給を心がけるとよいでしょう。
毎日身体に取り入れるお水には、安全で美味しくコスパ抜群の浄水器WACOMSをおすすめします。
毎日のちょっとした心がけと、コツコツ続けるケアが、未来の肌の美しさをつくります。
今日から少しずつ、肌にやさしい生活を始めてみましょう。
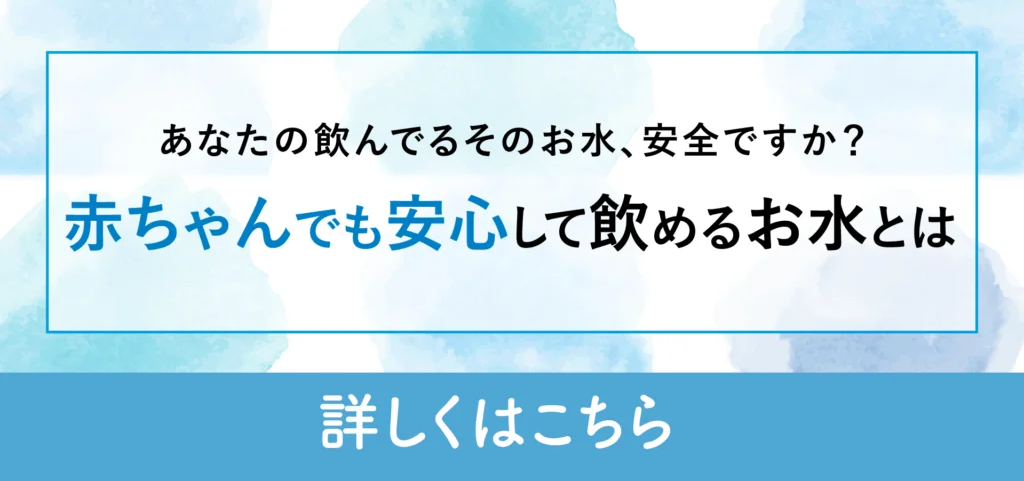
- ポーラ・オルビスグループ | ポーラ化成が男性の肌を徹底調査 ↩︎
- 筑波大学 | ヒトの体の水の代謝回転量を予測する式を世界で初めて発明 ↩︎
- Dietary water affects human skin hydration and biomechanics ↩︎
- Does dietary fluid intake affect skin hydration in healthy humans? A systematic literature review ↩︎
- 田園調布中央病院広報誌 | T O P I C S : 肌 の 乾 燥 を 防 ぎ ま し ょ う ↩︎
- 化学製品 PL 相談センター | 日焼けと紫外線 ↩︎
- 環境省 | 紫外線環境保健マニュアル2008 ↩︎
- 日本香粧品学会誌 | 化粧品の種類と使い方 —スキンケア化粧品— ↩︎
- はるかクリニック | 紫外線について ↩︎
- 日本香粧品学会誌 | セラミドに着目した敏感肌のスキンケア ↩︎
- 日本化粧品技術者会 SCCJ | 化粧品用語集 ↩︎
- 運動習慣と生活習慣が顔面表皮の水分量に及ぼす影響について ↩︎
- Exercise-stimulated interleukin-15 is controlled by AMPK and regulates skin metabolism and aging ↩︎
- 特定非営利活動法人 日本禁煙学会 | 第 4 巻第 4 号 2009 年(平成 21 年)8 月 25 日 ↩︎
- 株式会社ポーラ | 水分量を保つライフスタイルは「質の良い睡眠」 ↩︎
- 日本香粧品学会誌 | 主観的睡眠状態と肌状態との関連 ↩︎
- 空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集 | 非敏感肌・敏感肌女性に対する湿度の影響評価 ↩︎
- 空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集 | 暖房時の室内温熱環境が皮膚水分量と熱的快適性に与える影響 ↩︎
- 真野千夏 | 分子量の異なるヒアルロン酸の経口摂取による老化皮膚の改善 ↩︎
- 日本香粧品学会誌 | シワ形成メカニズムと抗シワ製品 ↩︎
- 森永乳業 | アロエステロール®含有ヨーグルト摂取による 皮膚水分量および皮膚弾力性の増加を確認 ↩︎
- 日本栄養・食糧学会誌 | アロエベラ由来植物ステロールの新規保健機能研究とその応用 ↩︎
- 日本食品科学工学会誌 | コラーゲンペプチド経口摂取による皮膚角層水分量の改善 効果 ↩︎
- 皮革科学 | 天然素材コラーゲンの機能性 ↩︎
- 食品安全委員会 | <参考資料> ↩︎
- 化粧品成分オンライン | リコピンの基本情報・配合目的・安全性 ↩︎
- カゴメ株式会社 | リコピンのさらなる可能性 ↩︎
- 帝京大学 医療技術学部看護学科 福士 泰世 | 放射線治療の 副作用に対する トマトジュースの寄与 ↩︎
- Beauty from within: Improvement of skin health and appearance with Lycomato a tomato-derived oral supplement ↩︎
- Topical lycopene emulgel significantly improves biophysical parameters of human skin ↩︎
- フジッコ株式会社 | 「肌の水分量、バリア機能(うるおいを保つ力)、弾力の維持」で 幅広い女性の肌の悩みにアプローチ ↩︎
- 江川 麻里子 | 分光測定に基づくヒト表皮水分の評価 ↩︎